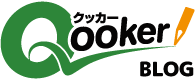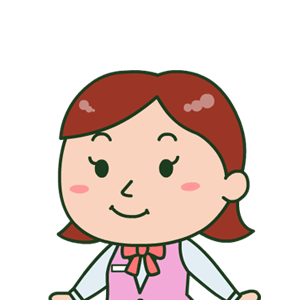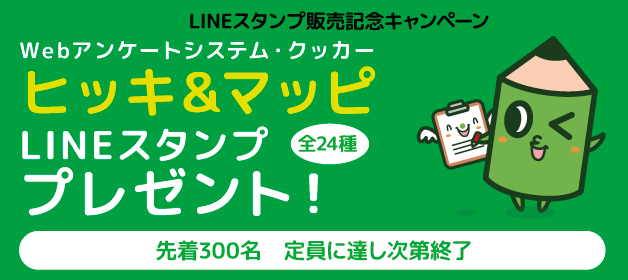やっと秋になったと思ったら、涼しいというより寒い日も。
四季を楽しめるのが日本のよさ。特に春と秋はうつろう美しい自然景観含め、
レジャーに最適な季節なのですが、近年、春も秋もぐっと短くなったような気がします。
それでも、気温が急に下がると紅葉は美しくなりますし、今年もとっても楽しみです。
さて、そんなレジャー先でやはり増えたなと実感するのがペット連れの旅行者。
先日の投稿でもご紹介しましたが、一般社団法人ペットフード協会調査では
2023年時点で犬の飼育頭数は約750万頭、2013年の約600万頭と比較して約25%増加しているもよう。
ペットと一緒にレジャーを楽しみたいという方は増えているのでしょうね。
旅先ではベビーカーならぬペットカートと一緒の方が目立ちますし
また、レジャー施設にドッグランやペットと一緒に入れるカフェやホテルも増えました。
ペットにとっても慣れない車や電車での旅は疲れるかもしれませんが
都会では安心して走り回れるところも少ないでしょうから、
広い旅先で元気に走り回るペットたちを眺めていると、こちらも元気になってきます。
こうしたペット連れの旅は「ペットツーリズム」と言われているそうで、
矢野経済研究所の調査によると、2022年度の国内ペット関連市場規模は1.7兆円超えだそうです。
特に、愛犬との旅行市場は2020年約400億円から、
2023年には約650億円、約1.6倍に拡大したもよう。
ちなみに、ペット同伴の平均客室単価は、一般的な旅行者よりも2~3割も高いそうで期待大。
(※楽天トラベル「ペットと泊まれる宿特集・平均単価比較データ(2022年)参照」
https://innconnect.jp/pet-tourism )
プランには、ペット用アメニティ、ペット用の夕食オプション、写真撮影サービス、
貸切ドッグランといったアップグレードプランもあるそうで、
ペット出費を惜しまないメインターゲットが楽しめるプランになっているものも多いもよう。
そんな中、関する興味深い調査を発見しました。
「秋レジャーと車中泊に関する調査2025」
(ホンダアクセス2025年10月発表)
https://www.honda.co.jp/ACCESS/press/2025/pdf/hac2025102301.pdf
■愛犬を連れてレジャーに行ったことがあるか (単一回答形式)
(対象:これまでに犬を飼ったことがある人 458名)
「ある」
・全体 14.8%
・20代 56.7%
・30代 50.0%
・40代 44.2 %
・50代 38.3%
・60代 37.4%
■愛犬と一緒に楽しみたいレジャー
(犬を飼っていて今年の秋に愛犬を連れてレジャーに行きたいと思う人 125名)
1位「ドッグラン」54.4%
2位「ドッグカフェ」52.0%
3位「キャンプ」 32.0%
4位「バーベキュー」31.2%
5位「温泉」28.0%
■愛犬を連れてのレジャーでは、クルマにどのような愛犬用アクセサリーがあると
便利だと思うか (複数回答形式)
(対象:これまでに愛犬を連れてレジャーに行ったことがある人 205名)
1位「ボックス型シート(ドライブボックス)」30.2%
2位「シートマット・シートカバー(汚れ・抜け毛付着防止)」 26.8%
3位「ドライブセーフティネット(後部座席から運転席に来られないようにする防護ネット)」25.9%
4位「ウォーターボウル」24.9%
5位「スペース ボード (座席下への落下防止)」23.4%
さて、今回の「ワンポイント★プラス」は…
「調査項目同士の比較分析」についてです。
本調査では、先ほどご紹介した「愛犬を連れてレジャーに行ったことがあるか」という設問があります。
下記の設問と同様に年代別に調査結果を公表しています。
■愛犬を連れてお泊り旅行をしたことがあるか (単一回答形式)
(対象:これまでに犬を飼ったことがある人 425名)
「ある」
・全体 32.2%
・20代 42.2%
・30代 44.4%
・40代 35.8 %
・50代 24.5%
・60代 23.4%
この場合、愛犬を連れた「レジャー」と「お泊り旅行」の関係性を整理しておく必要があります。
レジャーのなかに「お泊り旅行」が含まれている、より大きな概念であるという整理が
調査側と回答者側で共通理解されているように設計できているとも言えます。
本調査では、いずれの年代でも「レジャー」実施者よりも「お泊り旅行」実施者は少ないため、
日帰りレジャーは実施したことがあるが「お泊り旅行」はしたことがないということが想定されます。
この差異に対して、市場の白地算出も可能となりますし、マーケティング素地とすることも可能となります。
今回の場合は比較的わかりやすい項目同士の関係性となりますが、
回答者の理解が難しい調査項目での比較の際にはそれぞれの定義を明確に設計しておくことが必要です。
ぜひ、今後の調査設計の際の参考にしてみてください。
※皆様からのご質問やご意見もお待ちしています。どうぞお気軽にユッキにご連絡ください。