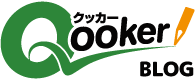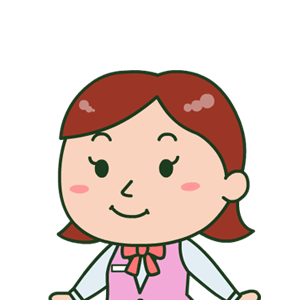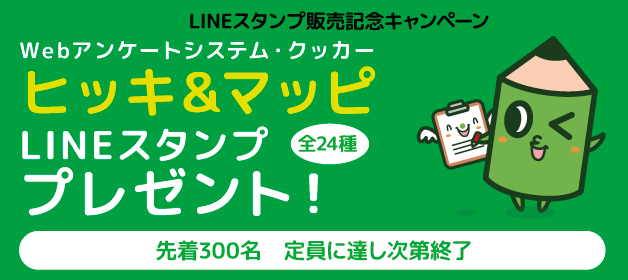近年、便利でもあり、ややこしくもある決済手段の多様化。
レストランやスーパー、コンビニでも支払い手段が多すぎて迷うことや、
SUICAや●●Payなど、それぞれいくら残金があったか混乱してしまうという方も
多いのではないでしょうか。
MMD研究所「2025年7月決済・金融サービスの利用動向調査」によると、
https://mmdlabo.jp/investigation/detail_2474.html
普段利用している支払い方法に関して、直近1ヶ月の支払い方法の割合では、
「現金」が74.9%と最も多く、次いで「クレジットカード」が53.0%、
「QR・バーコード決済」が46.7%だったそうで、まだまだ現金が手放せない現実がありそうです。
また、気になるQR・バーコード決済利用については、
「PayPay」が65.2%と最も多く、次いで「楽天ペイ」が35.9%、「d払い」が28.2%。
1人当たり複数の決済機能を活用していることも分かります。
さて、そんななか、いよいよ国内ではこの秋、法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコイン発行が
初めて実現する見通しとなり、何かと話題になっているデジタルマネーの世界。
では、いったいステーブルコインとは何なのでしょう?
ステーブルコインとは、暗号資産のようなBTCやETH、XRPなど変動性のある資産とは異なり、
米ドル、米国債等に裏付けられその価値の変動を抑え、価格が常に安定している(Stable)であることが特徴。
米国では既に、こうした米ドルの裏付けによるステーブルコイン(USDT・USDC)のほか、
アルゴリズムを利用するステーブルコインなども各種存在。
7月にトランプ政権は、ドル建てステーブルコインの普及を目指すGENIUS法を成立。
米投資銀行のシティグループは、米国内での規制変化がブロックチェーン技術の導入を加速し、
2030年までに市場規模が3.7兆ドル(約500兆円)に達する可能性があると予測しているそうで
(https://coinpost.jp/?p=611334)
国際決済銀行(BIS)が5月末に公表したリポートによると、2024年にステーブルコインの発行体が購入した米短期国債は約400億ドルに上るとされており、ステーブルコインの発行企業は今後、米国債の買い手としても、その存在感を高めているそうです。
さて、今月の「気になる★数字」
「JPYCステーブルコイン
今後3年間で1兆円発行!?」
についてみてみましょう。
https://moneyworld.jp/news/05_00184811_news
日本では2022年6月に成立した「改正資金決済法」がステーブルコインの認可の根拠となっていますが、
この法律は、グローバルにステーブルコインの利用が拡大する中で、利用者保護とマネー・ローンダリング(AML)対策を強化するために制定されたようです。
ステーブルコインを「電子決済手段」の一つとして定義し、発行者を銀行、資金移動業者などに限定して、裏付け資産の保全を義務付けることで、利用者が安心して使える環境を整備することも目的のひとつ。
そんななか、フィンテック企業のJPYCが8月、銀行以外で送金(為替取引)サービスをする
「資金移動業」登録業者として認可され、今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で実現する見通しのもよう。
今後3年間で1兆円分の発行を目標とすることなどが報じられています。
JPYCの場合には、裏付け資産として預貯金や国債を保有することによって価値が保全されるそうで、
日銀に代わる国債保有者を模索している日本国内で、あらたな国債の保有者としての期待も高まっているそうです。
また、ステーブルコインの強みは、利用手数料を低く設定することができること。
海外送金やサービスなどのマイクロペイメント(少額決済)などの手数料も
これまでの決済方法より抑えられることが想定できるため、多様な利用が見込まれているようです。
今後の金融業界の変化にアンテナを高めに立てておかなければと思う今日この頃です。
ぜひ、この記事のお問い合わせや感想など、どうぞお気軽にユッキにご連絡ください。